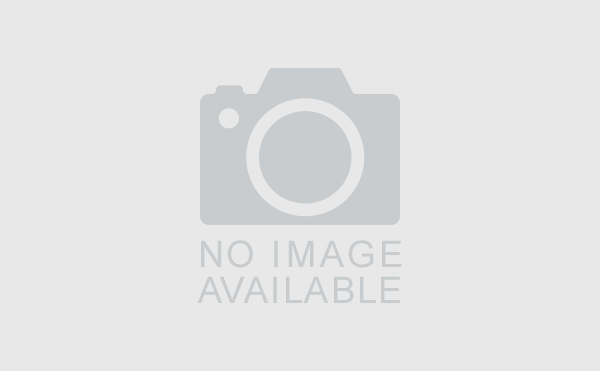28年地中にあった単管パイプ架台の劣化について 1
28年地中にあった単管パイプ架台の劣化について 1
浅川第二太陽光発電所


1997年太陽光発電所の実証施設として、単管パイプを用いた、太陽電池設置架台を考案し、実用性と耐久試験を踏まえた上で、実証実験が終了後の撤去までを視野に入れた設計思想で組み上げた、単管パイプ太陽電池設置架台になります。

このほど、太陽光発電所としての実験終了により、撤去に至りました。
当初考えていた、撤去方法と実際の計画との差異は、あまりなく予定した手順で解体を進めることができました。

解体を始めて、改めて28年と言う年月の長さを、体力の衰えとともに強く感じる解体撤去作業になりました。
脚立を使い、2mの高さに上がると、膝が笑い、高所感覚に順応するまでに、二日程必要になりました。28年前には、片手で取り扱えた、太陽電池パネルが、両腕で支えての作業になっていました。
太陽電池の撤去作業の前に、太陽電池からの発電電流は、直流となっているので、各セクションで、OFラインにしますが、太陽電池は複数枚がワンセクションになっているので、感電事故防止のために複数枚の中央部分で断線します。


撤去作業は、上部構造からの撤去となります。
構造組み立てには、主要部分は直行クランプ・自在クランプで組み上げてあるので、手作業で解体できます。(ラチェットレンチ・電動工具等)太陽電池の取り付け架台には、DP1とUボルトで対応してあり、太陽電池固定のステンレスネジは、問題なく緩みました。
こちらは、地上部、埋設部を解体した写真になります。地上部の単管パイプには、28年間を感じさせる程の変化はあまり見られませんでしたが、地中部分については、いくつか、興味深い部分がありましたので、紹介させていただきます。
この架台の特徴は、単管パイプを使用し、地盤改良を行わない伏せ式である点です。では指示地盤圧力や風対策等については、井桁組み構造と杭による押さえで対応する構造になっており、4mの田の字構造で指示地盤を作り、横移動に対しては、4mの田の字、四隅に地中70cmまで杭を打ち込みクランプで固定するのが基本な構造となっております。
今回、注目した点は、支持地盤形成構造の田の字(直置き)部分と地中深くに打ち込んだ杭の部分(約70cm)と、上部の太陽電池を支えるための支持部材部分(地中30cm)の単管パイプの錆状況についての比較資料となります。

こちらの写真の単管パイプは、支持地盤形成のために田の字に組んだ据え置きパイプの錆の発生状況になります。
単管一面に均一の錆と、船底につくフジツボや牡蠣のように点々とサビの塊が確認できるのが特徴です。
錆落としをしてみたところ、金槌で殴打すると、サビの塊は剥ぎ落とすことが容易にできました。

こちらの写真は、地中70cmまで打ち込んであった固定杭を引き抜いて、錆の状況確認をしている写真になります。
48.6mmが70mm近くまで錆で、太く成長しておりましたので、縦横方向への応力対応能力が、初期の設定値の倍近くに向上していたと思われます。
こちらの錆を金槌で殴打すると、約1cm以上の厚さとなった錆が取れます。
単管を保護するように、ほぼ均一に錆が成長しており、杭を引き抜く時に大きな抵抗となりました。

引き抜いた直後に殴打して、錆を取ると
錆の落ちた部分では、ほとんど腐食されていない状態と、見て取れる単管パイプが現れました。太陽電池のフレームがアルミ枠なので、電食による、錆の発生は予測していましたが、これほど、綺麗な保護錆膜が形成されているとは思いませんでした。
地中深さによる錆の成長のようす。

地中70cmと40cmの比較写真
地中30cm付近から、酸化被膜・錆びの成長が急速に成長しているのが確認できます。
前記の通り、錆の成長により、支持地盤の強度が、年単位で成長していったと考察されます。

こちらの写真は、地中に埋設していた部分を比較対象の為に1箇所に集めて、各部材の埋設部の錆の発生状況が確認できるようにした写真になります。
深さとともに、錆の発生が比較できるようにメジャーと共に撮影いたしました。
地表部分から30cm付近から錆の成長が拡大しているのが確認できます。

対照的に、単管パイプを結束に使用した
自在・直行クランプは、地中部分については錆と腐食が進み、強度の低下と、解体時には
潤滑剤の使用が必要なほどに錆が成長しており、再使用は不可能な部材となりました。

対照的なのが、地上部分で、場所によっては新品同様と間違える直行・自在クランプもあるほどで、殆どのクランプが再使用可能な状態にあり、28年間の地中と地上にあった
環境の違いを、まざまざと比較実感できる
資料資材となりました。

自然環境の力を思い知ったのが、こちらの 日射量計です。
日射量観測は、10年前に終了しており、機器は、28年間野ざらし、結果、紫外線や自然環境の猛威にさらされ、通信ケーブルの被覆が禿げてしまいました。
今回の撤去作業においては、太陽電池架台の自然劣化に重点を置いて、説明してまいりました。
太陽電池からの送電ケーブル等については、著しい自然劣化は見られませんでした。今回の撤去原因となった本題については、次回、以降、纏めましてご報告いたします。
長文にお付き合いいただきましてありがとうございました。
浅川太陽光発電所
所長 浅川初男
2025,11